あなたは「裏遍路道」という言葉をご存知だろうか?
かつて不治の病と恐れられた病を患った者たちが歩かされた遍路道、それは一般的な遍路道ではなく“裏遍路道”と呼ばれる別の道だったのだ。
年間15万人ほどが訪れることで知られる四国遍路だが、言うまでもなく通常は整備された道を徒歩や車で移動する。しかし、当時はそことは異なる道を行き来する者たちの姿があったのだ。
そこで今回は四国霊場に隠された差別の歴史「裏遍路道」という禁忌にせまる。
かつて本来の遍路道とは異なる道があった
image: www.city.sakaide.lg.jp/
四国霊場「遍路道」が全国的に知られ、多くの人が訪れるようになったのは、高野山・信念の著書「四国邉路道指南」に“八十八ヶ所”と記載されたことがキッカケ。その後、伊勢参りなどと並んで庶民の人気を集めるようになり、四国や関西だけでなく、全国の人々が巡礼するようになった。
■関連書籍
しかし、集まった人々のなかには四国を死に場所と定めて訪れる者もいたのだという。
かつて不治の病と恐れられたハンセン病などの病を患った者たちがそれに該当するのだが、彼らは通常の遍路道を歩く以外にも、世間から蔑まれる病を患っていたこともあり、いわゆる“裏遍路道”と呼ばれる異なる道を歩かされたようだ。
なお、その裏遍路道は差別用語で「か○たい道」などとも呼ばれ、自分の体が朽ち果てるまで四国をまわり続けるハンセン病の遍路たちは季節ごとに四国の中を移動したという。
冬は高知県の三十二番札所・禅師峰寺からほど遠い砂浜や洞窟などで過ごし、春になると雨の多くなる高知を離れて、愛媛や香川、徳島に向かったそうだ。
“裏遍路道”ができた要因は「あらゆる差別」だった
image: www.yushodo.com/
裏遍路道ができた過程には、ハンセン病に対しての差別もあったが、それと同時に江戸時代を通じて特に土佐藩では遍路たちを厳しく取り締まったことにも理由があったという。そう、裏遍路道は必ずしも差別のみが原因で出来上がったものではないのだ。
というのも、江戸時代末期の日本は飢餓が頻発し、諸国からハンセン病だけでなく、食い詰めた「乞食遍路(差別用語)」と呼ばれる者たちが土佐に流れ込んでいた。なお、その者たちのなかには聖地巡礼ではなく、ただ食にありつくために四国をまわり強盗をはたらくなどの不埒な者も多かったため、当時の遍路は差別的な目で見られていた可能性があるのだ。
なお、当時の遍路を知る地元民の証言によると「(当時の遍路は)着のみ着のままの汚い格好をして、家の縁側とかで勝手に寝ているような怖いイメージ」なのだという。
このようにハンセン病患者への差別だけでなく、遍路そのものへの差別も“裏遍路道”には込められているのである。
四国霊場に“裏遍路道”が出来上がった背景
image: www.pref.ehime.jp/
当時、乞食遍路には世界的に数千万人もの死者を出したインフルエンザなどのウイルスを持ち込み、村に死者を出すこともあり、そうした理由もあって土佐藩などは遍路を厳重に取り締まった。
その影響から、当時の遍路たちは通常の遍路道を歩くことができないため、人知れず山の中に獣道のような裏遍路道を歩かざるをえなかったといえよう。
なお、現在も高知県の一部には人ひとりが通ることができる程度の尾根と谷を結んでいる山道がある。無論、今は誰も通らない木々に覆われた山道になっているが、こうした道が“裏遍路道”と呼ばれたのである。
現代の私たちには見えない道が、四国の山中には無数に走っていて、日本の悲しい差別の歴史を今に伝えているのだ。
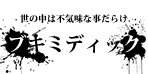




 世界のあらゆる“不気味な情報”を管理人独自の視点でアップしていくサイト。ほら、あるじゃないですか?世の中には不気味な人、不気味な場所、不気味な画像。
ただし、当サイトは“不気味な情報”のみを専門に取り扱うものの、グロテスク関連ものを掲載するアングラ系ではありません。あくまで不気味な情報を掲載するコンテンツです。
それではごゆるりと。
世界のあらゆる“不気味な情報”を管理人独自の視点でアップしていくサイト。ほら、あるじゃないですか?世の中には不気味な人、不気味な場所、不気味な画像。
ただし、当サイトは“不気味な情報”のみを専門に取り扱うものの、グロテスク関連ものを掲載するアングラ系ではありません。あくまで不気味な情報を掲載するコンテンツです。
それではごゆるりと。









 触れられるものはいつか滅びる。だからこそ、今目にしているすべての物事を自身のモノサシで測ってはもったいない。引き出しが足りないなら増やせばいいだけ。ありきたりな日々を作っているのは自分自身だ。
触れられるものはいつか滅びる。だからこそ、今目にしているすべての物事を自身のモノサシで測ってはもったいない。引き出しが足りないなら増やせばいいだけ。ありきたりな日々を作っているのは自分自身だ。
この記事へのコメントはありません。